
Since 2003/1/1
もくじ
・地名の由来
・五明塚と開化天皇
・神王社と神大根王
・北野神社と大碓命と
押黒之弟日子王
・神大根王の子孫たち
NEW
・栗栖太里戸籍 NEW
1:三野部と人口
2:栗栖太里の位置
3:婚姻制度
4:造籍と寄人
5:古代人の個人名
6:福祉と賤民
7:その他の戸
資料:養老令等
・条里制
・地蔵菩薩と馬頭観音
山神等の石仏
・見延河原合戦
・見延城跡
・お松が墓と松林寺
と観音寺
・糸貫川(伊津貫川)
・川はどこに
・濃尾大震災
・明治20年見延村絵図
・パワースポット・マップ
・倭人伝と邪馬台国 NEW
・質問・連絡

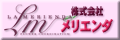
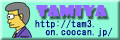

歴史書から想像する昔の見延
〜考古学的根拠(物的証拠)に乏しい資料〜
本資料は、岐阜県本巣市見延に関わる歴史的な資料を構成したものです。考古学的な物によるエビデンスがある訳ではなく、書物によるものが多く推測(妄想)的な内容も多くあります。
この資料は、抜粋した内容と個人的な想像とを区別して作りましたが、どちらも正しいとは限りませんので疑って読むようにしてください。
漢字が普及していない8世紀以前では、文章はもちろん、文字表記の決まりはなく、発音を記録するための漢字であったため、1つの人名地名でさえいくつかの表記がありました。大昔の書物は漢字の意味だけでなく「音(読み)」に着目して読むとよいでしょう。
 お知らせ
お知らせ
トップに戻る
日付 お 知 ら せ R07/10/01 重要なお知らせです。当サイトのURLが変わりました。
「http://〜」から、「https://〜」になります。//の後ろは変わりません。
プロバイダNiftyのセキュリティ強化のためなのですが、お気に入り等のリンクを登録されている場合は、変更(再登録)をお願いします。当面は自動で「https://〜」に移動しますが、来年辺りから、新しいURLでないと移動しなくなります。
新しいURLは、https://tam3.on.coocan.jp/minobe.history/R07/10/01 新エピソード「魏志倭人伝と邪馬台国」を公開しました。 R07/02/17 新エピソード「濃尾大震災」を公開しました。 R06/10/05 「神大根王の子孫たち」の中に「国造千代」や「美濃直玉虫」のエピソードを追加しました。 R06/09/02 「神王社」の話から「神大根王の子孫たち」という話を独立し、内容を充実しました。 R06/07/21 新エピソード「栗栖太里戸籍」に「6:福祉と賤民」「7:その他の戸」を追加しました。 R06/06/09 「栗栖太里戸籍」の「1:三野部と人口」に「戸」の概念についての節を追加しました。 R06/06/01 新エピソード「栗栖太里戸籍」に「5:古代人の個人名」を追加しました。 R06/01/31 「神王社と神大根王」の中に新エピソード「的場」の節を追加しました。 R04/10/16 新エピソード「栗栖太里戸籍」を造り始めました。 R03/11/16 新エピソード「川はどこに」を追加しました。 R03/11/13 「条里制」にエピソード「東西南北の方位」に関する内容を追加しました。 R03/02/09 新エピソード「明治20年見延村絵図」を追加しました。 R02/08/16 質問フォームの送信方式を変更しました。「CGI RESCUE」という無料フォームデコードサービスに変更しました。 R01/09/01 本サイトのURLを変更しました。 H29/09/10 新エピソード「条里制」を作り始めています。 H29/01/01 新エピソード「見延河原の合戦」を追加しました。 H28/09/11 本サイトを公開しました。
 内容一覧
内容一覧
トップに戻る
もくじ 主 な 内 容 地名の由来 「日本」という国名、岐阜や本巣などの地名、本サイトのテーマである「見延」、及び、その小字名の由来などについて調べてみました。「見延」にはすごい由来があるのです。 五明塚と開化天皇 大きな戦がなくなった江戸時代、農民は農業生産に挑んでいきました。井水のトラブルもありましたが、新開地を切り開き生産量を増やしていった一方で、犠牲になってしまったものもあるようです。 神王社と神大根王 神社に残る文書は火災で一切が焼け、由緒等は、伝承による推測以外分かりませんが、祀られている神は、古事記や日本書紀に載っている人だったのです。 北野神社と大碓命と
押黒之弟日子王北野神社には多くの合祀社がありますが、中には意外な神社もあるのです。これもまた祀神は、古事記や日本書紀に載っている人だったのです。 神王根王の子孫たち 神大根王の後、本巣の王の子孫たちはどうなっていったのでしょうか。それを探っていきますが、残念ながら見延から少し離れるかも知れません。 栗栖太里戸籍 本簀郡栗栖太里戸籍というのは、1300年前の戸籍です。ある目的のために全国的に作られた時期があるのです。戸籍ですから、そこに記録された個人が生きた証しだけでなく、その時代の様子も見えてきます。見延の由来にも触れます。 条里制 本巣市や南に隣接する瑞穂市には,十四条や十九条といった地名が残っており,この地に条里制がしかれていたのは間違いないでしょう。では,見延は何条何里だったのでしょうか。 地蔵菩薩と馬頭観音
山神等の石仏集落の中や道端には、よく石仏が設置してあります。概ね今回紹介する3種類の石仏が多いようです。
時々花が添えられ誰かがお参りしているようですが、しかし、一体何のための石仏なのでしょうか。見延河原合戦 1536年(天文5年) 斎藤道三率いる土岐頼芸軍と土岐頼武軍が見延の河原で戦っています。どんな戦(いくさ)だったのでしょう。 見延城跡 城といっても天守閣のあるような城ではありません。「砦」と言った方がよいかも知れません。しかし、この砦が築かれた場所に大きな秘密があったのです。 糸貫川(伊津貫川) 糸貫川は見延の東に隣接しており,見延に住んでいた人々のくらしに深く関わっていました。また,古来より歌枕の名所になっており,都にまで伝わるほど,景色がよかったようです。どんな歴史が隠れているのでしょう。 川はどこに 見延の東には糸貫川が流れていますが、西にはかつて「五明川」が流れていました。その他、見延の中を流れている寺川や馬伏川などはどこに流れていくのでしょうか。 お松が墓と松林寺
と観音寺お松が墓には、ユニークな伝説が2つ残っています。1つはフィクション、もう1つはノンフィクションのようです。
観音寺は今、倒れかかっています。倒壊は時間の問題でしょう。歴史は古く菅原道真の時代まで遡ります。濃尾大震災 明治24年(1891年)の濃尾大震災は、この地方に大きな傷跡を残しました。災害も歴史の一部として、少し調べてみました。 明治20年見延村絵図 明治初期、政府は租税徴収のため地積測量を開始し課税対象を明確にしようとしました。その結果、できたのがこの地図です。 パワースポット・マップ これまでの記事を地図の上で示します。著作権の関係で耕地整理前の古い地図になります。 魏志倭人伝と邪馬台国 見延の歴史とはかなり離れた話となります。理系の視点で、魏志倭人伝を読んでみました。 質問・連絡 質問や連絡のある方はフォームに入力して送信してください。後日、回答を返信します。
 質問・連絡フォーム
質問・連絡フォーム・質問や連絡のある方は下のフォームに入力して送信してください。後日、回答を返信します。トップに戻る
・必要事項を入力し、下記「操作」の手順で送信してください。
・質問されても、私も専門家ではないため、期待する回答できないことも多いと思います。
・すぐには回答できない場合もあります。少なくとも2〜3日はお待ちください。